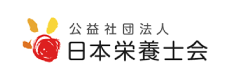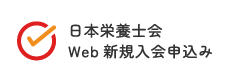栄養士会について

会長挨拶
食と栄養の指導・支援を通して、県民の健康づくりに貢献します。
令和5年度に開催されました定時総会の役員改選により栄養士会長を拝命いたしました。県民の皆様、会員の皆様にとって魅力ある愛媛県栄養士会を目指して、理事はじめ会員の皆様のご協力をいただきながら、会の活動に努めてまいります。何卒よろしくお願い申し上げます。
愛媛県栄養士会は、昭和22年「日本栄養士会 愛媛県支部」として発足しました。昭和61年1月16日「社団法人 愛媛県栄養士会」として認可され、平成25年4月1日「公益社団法人 愛媛県栄養士会」として活動しています。
本会は、愛媛県民の健康及び福祉の増進に寄与すること、食と栄養に関する実践活動を通して、県民の健康増進と疾病の予防を計り、地域の栄養改善、福祉・医療、公衆衛生の向上を図ることを目的とし、すべての人びとの「自己実現をめざし健やかによりよく生きる」 とのニーズに応え、保健、医療、福祉及び教育等の分野において、食と健康の専門職としての倫理と科学的根拠かつ高度な技術に基づく諸活動を通して、県民の健康増進、疾病の予防及び生活の質の向上に寄与することにより、社会的責務を果たすことを使命としています。
今後も、食と栄養の指導、支援をとおして県民の健康づくりに貢献できるよう努めてまいります。各関係機関、各団体の皆様方の一層のご支援・ご指導をお願い申し上げます。
公益社団法人愛媛県栄養士会
会長永井 祥子
管理栄養士・栄養士倫理綱領
管理栄養士・栄養士倫理綱領(第2版)
(制定 平成14年4月27日 改定 平成26年6月23日)
本倫理綱領は、すべての人びとの「自己実現をめざし、健やかによりよく生きる」とのニーズに応え、管理栄養士・栄養士が、「栄養の指導」を実践する専門職としての使命と責務を自覚し、その職能の発揮に努めることを社会に対して明示するものである。
- 管理栄養士・栄養士は、保健、医療、福祉及び教育等の分野において、専門職として、この職業の尊厳と責任を自覚し、科学的根拠に裏づけられかつ高度な技術をもって行う「栄養の指導」を実践し、公衆衛生の向上に尽くす。
- 管理栄養士・栄養士は、人びとの人権・人格を尊重し、良心と愛情をもって接するとともに、「栄養の指導」についてよく説明し、信頼を得るように努める。また、互いに尊敬し、同僚及び他の関係者とともに協働してすべての人びとのニーズに応える。
- 管理栄養士・栄養士は、その免許によって「栄養の指導」を実践する権限を与えられた者であり、法規範の遵守及び法秩序の形成に努め、常に自らを律し、職能の発揮に努める。また、生涯にわたり高い知識と技術の水準を維持・向上するよう積極的に研鑽し、人格を高める。
栄養士会の概要
愛媛県栄養士会は昭和22年「日本栄養士会 愛媛県支部」として12名の栄養士で発足し、昭和61年1月16日には「社団法人 愛媛県栄養士会」として認可され、その後、平成25年4月1日「社団法人 愛媛県栄養士会」を名称変更し、移行したことにより「公益社団法人 愛媛県栄養士会」として活動を続けております。当会では、次の目的を果たすことができるよう、また、県民に開かれた栄養士会となるよう日々社会的責務を果たすよう努めております。
目的
食と栄養の指導・支援を通して、県民の健康づくりに貢献します。
- 食と栄養に関する実践活動を通して、県民の健康増進と疾病の予防を計ります。
- 地域の栄養改善、福祉・医療、公衆衛生の向上を図ります。
事業概要
- 健康増進のための調査・研究及び各種健康づくり活動
- 県民の健康づくり施策への参加、協力、推進
- 県民参加のセミナー・講習会をはじめ、専門研修(非会員、一般県民も受講可)を開催
- 食育体験学習など食育に関する推進活動
- ホームページ、電子メールによる情報伝達と健康情報の発信
- 食に関する提言
組織・体制図
理事会を最高の決議機関とし、総務部・事業部・学術部の3部と各種委員会を設けて、本会の事業を執行している。また、各会員は、支部活動(5支部)と事業部活動(6事業部)に属し活動している。
ready役員名簿
令和7・8年度役員名簿(令和7年6月14日就任)
顧問
利光 久美子
代表理事(会長)
永井 祥子
代表理事(副会長)
山本 多津
代表理事(副会長)
元家 玲子
常任理事(総務)
山﨑 友美
常任理事(会計)
木村 麻美子
常任理事(書記)
森木 陽子
理 事(医療事業部長)
石田 美津子
理 事(学校健康教育事業部長)
髙橋 正子
理 事(研究教育事業部長)
栗原 和也
理 事(公衆衛生事業部長)
河野 洋子
理 事(福祉事業部長)
今井 亮太
理 事(フリーランス・栄養関連企業等事業部長)
宇佐 亮子
理 事(今治支部長)
河上 有希
理 事(宇和島支部長)
久保田 紀江
理 事(西条支部長)
小野 晋平
理 事(松山支部長)
宮崎 さおり
理 事(八幡浜支部長)
瀧野 晴香
理 事
髙橋 恵美
事務局長
利光 久美子
理事補佐
篠原 久実
理事補佐
田村 恵理
理事補佐
山本 ひろ子
理事補佐
井上 可奈子
監事
竹内 明久
監事
松本 孝子
令和7年6月25日現在
(順不同)
入会のご案内
公益社団法人 愛媛県栄養士会は、愛媛県内に勤務、または在住の管理栄養士・栄養士の資格をもつ者で構成され、食と栄養に関する専門家の集団です。入会することで日本栄養士会及び愛媛県栄養士会の会員となります。
入会のメリット
1.専門職業人としてのスキルアップ ・仲間づくり
各種研修会・講習会にお得な会員割引価格で参加できます。
基礎的な知識・技術をはじめとして、それぞれの専門分野の最新の情報や技術について学習するとともに、同じ職域の先輩や多くの仲間たちと、会員同士の情報交換をすることができます。
2.栄養に関する情報収集
- 毎月「日本栄養士会雑誌」が届きます。
- 「会員専用ページ」から最新情報を入手できます。
- 愛媛県栄養士会から研修会などの情報を入手できます。
3.安心の保険
管理栄養士・栄養士の業務には重い責任が伴う場合があります。
万が一に備えて、入会と同時に、「栄養士賠償責任保険」に自動加入となり、 最大1億円の補償が受けられます。
(日本栄養士会のホームページにリンクします)
入会手続きについて
入会のお申込み後、年会費の納入をされることで入会手続きができます。
Webからのお申込み
画面上で入会申込ができ、Web入会申込の場合、クレジットカード決済も選択できます。
(日本栄養士会のホームページにリンクします)
または
郵送等でのお申込み
入会申込書に必要事項を記入し、下記事務局までメールまたはFAX、郵送してください。
郵送先
公益社団法人 愛媛県栄養士会
〒790-0003 愛媛県松山市三番町4丁目3-9 香川ビル2F (アクセス >)
TEL:089-946-0734 /
FAX:089-946-0702
E-mail:
過去に入会経験があり、当時の会員番号がご不明な場合
お電話でのご連絡 または お問い合わせフォームに入力して送信してください。
TEL:089-946-0734
(平日10時~16時)
会費について
会費は、年に1回納入の年会費になっています。会員資格の有効期限は1年間とし、毎年4月1日に更新いたします。年度途中いつでも入会でき、いつ入会されても、4月1日から翌年3月31までの1年間になります。年度途中で入会された場合、毎月発行される「日本栄養士会雑誌」は4月号からの分がまとめて届きます。
次年度会費は、4月30日までに納入してください。
- 初年度会費・・・・16,000円
- 継続会費・・・・・15,000円
年会費内訳
・入会金(初年度のみ) 1,000円
・愛媛県栄養士会:会費 8,500円
・日本栄養士会:会費 6,500円
振込み先
伊予銀行大街道支店 普通 1701187
公益社団法人 愛媛県栄養士会
ゆうちょ銀行 口座番号 01670-2-8751
公益社団法人 愛媛県栄養士会
※お振込みの手数料はご負担ください。
各支部の詳細
(1)西条支部
四国中央市、新居浜市、西条市
(2)今治支部
今治市、上島町
(3)松山支部
松山市、伊予市、東温市、松前町、砥部町、久万高原町
(4)八幡浜支部
八幡浜市、大洲市、西予市、内子町、伊方町
(5)宇和島支部
宇和島市、松野町、鬼北町、愛南町
各事業部の詳細
医療
病院等の医療施設、診療所、歯科医療、保険薬局等に勤務する会員
福祉
児童福祉施設、老人福祉施設、社会福祉施設等の栄養・給食管理部門等に勤務する会員
学校健康教育
幼稚園、小・中学校・特別支援教育諸学校等において栄養・給食管理にかかわる部門等に勤務する会員
研究教育
管理栄養士・栄養士養成施設等教育機関(大学・短大・専門学校)、企業の研究機関等に勤務する会員
公衆衛生
都道府県庁、保健所、保健センター、市町村等に勤務する会員
フリーランス・栄養関連企業等
自営、フリーで社会活動をしている会員及び、企業(給食会社、食品会社等)、事業者、矯正施設、自衛隊等に勤務する会員
※令和7年度の総会を以って地域活動事業部と勤労者支援事業部を統合し、「フリーランス・栄養関連企業等事業部」となりました。
勤務先・住所・その他の変更について
登録事項に変更があれば、日本栄養士会のマイページから変更が可能です。
もしくは変更届に必要事項を記入し、事務局まで提出してください。
退会手続きについて
次年度退会希望の方は、退会届に必要事項を記入し、事務局へ提出してください。
※会費自動引落(毎年4/1)の方は、解約手続きのため1月31日までに退会届を提出してください。
会員栄養士が配置されている施設
管理栄養士・栄養士は、病院・学校・保育所・高齢者施設・市町村保健センター・事業所など、いろいろな職場で活動しています。

医療事業部
病院や診療所で、病気の治療、合併症予防を目指し、栄養管理や栄養指導を行います。栄養アセスメント、モニタリングなど、個々に応じた栄養管理が重要視されており、医療分野でチームの一員として活躍しています。

福祉事業部
福祉職域の栄養士・管理栄養士は児童、高齢者、心身障がい者など福祉支援を必要とする方々へ食を通じてのサポートを行っており、各福祉施設や事業所、関係機関に配置されています。単に食事提供や栄養管理だけではなく、食育活動や食の楽しみのサポートなども食支援の一つです。必要な栄養量、食事の意味合いなどは年代や生活背景ごとに異なるため、それぞれの対象者に寄り添い、その人らしい食生活が送れるためのお手伝いをさせていただきます。
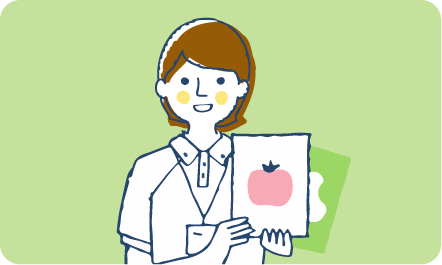
学校健康教育事業部
幼稚園・小中学校等に勤務し、給食管理と食に関する指導を行います。また、県市町の教育委員会に勤務する管理栄養士や栄養士は、県市町の学校給食に関わる指導に当たります。特に栄養教諭は、生きた教材である学校給食の管理と、それを活用した食に関する指導を行い、教職員や保護者、関係機関等との連携を図り、食に関する教育のコーディネーターとしての役割も果たしています。

研究教育事業部
研究教育事業部は、大学や企業などの研究室に所属している管理栄養士・栄養士で構成されています。大学は食や健康に関する科学的根拠をつくり発信すること、未来の管理栄養士・栄養士を育成すること等を通して社会や個人の健康づくりに寄与できる活動を行っています。企業では調査や実験から新しい発見を生み出し、新商品の開発等に関わっています。

公衆衛生事業部
公衆衛生事業部は、県や市町の自治体や保健所などで働く管理栄養士・栄養士で構成されています。保健師、看護師、事務職員などと連携して、食を通じて地域住民の皆様の健康づくりをサポートしています。仕事内容は、生活習慣病予防や離乳食の講習会、栄養相談、特定保健指導、給食を提供する施設への指導、社会環境の整備の促進など多岐にわたります。

フリーランス・栄養関連企業等事業部
フリーランスで活動する管理栄養士・栄養士が主に所属している事業部です。市町の特定保健指導、栄養教室、乳幼児健診をはじめ、医療機関での栄養指導、短大や専門学校の非常勤講師など、それぞれの会員が得意分野を生かして活動しています。乳幼児から高齢者までの全てのライフステージにかかわり、食に関する正しい知識の普及と、地域の健康づくりの支援を行っています。
各支部の紹介


宇和島支部
宇和島支部は、宇和島市・松野町・鬼北町・愛南町内に勤務または在住の管理栄養士・栄養士で構成されています。支部活動として、宇和島歯科医師会、宇和島市、宇和島市教育委員会主催の「お口から考える健康づくり教室」に他団体(歯科衛生士会・薬剤師会等)と後援・協力し、栄養・食事に関する相談等を行っています。支部の活動は、同じ地域で活動する仲間や他職種との「つながり」を持つ役割も担っています。

西条支部
西条支部は、西条市・新居浜市・四国中央市に勤務または在住の管理栄養士・栄養士で構成されています。支部活動は西条市では「男の料理教室」に講師として参加し料理の基本から作り方まで一緒に料理を行います。新居浜市では「生き生き健康フェスティバル」にて子ども向け食育クイズやゲーム、一般向けに血圧測定や食生活チェックの結果をもとに栄養相談を行っています。四国中央市では「地域ケア個別会議」に参加し管理栄養士の視点での助言提供を行っています。各市から依頼のあった案件に関して積極的に取り組んでいます。

松山支部
松山支部は、松山市・伊予市・東温市・松前町・砥部町・久万高原町内に勤務または在住の管理栄養士・栄養士で構成されています。社会活動として、R6年度「えひめ・まつやま産業まつり」に参加しました。R7年度からは「東温市健康フォーラム」に参加する予定です。食生活、栄養に関するパネル展示、パンフレット、レシピ配布、血管年齢・内臓脂肪測定等の結果をもとに、栄養相談などを実施し、市民等へ食に関する情報提供や食生活改善の支援を行っています。

八幡浜支部
八幡浜支部は、大洲市・西予市・八幡浜市・内子町・伊方町内に勤務または在住の管理栄養士・栄養士で構成されています。支部活動では、大洲市食育推進会議や、八幡浜市の健康イベントに参加協力しています。
(C) 2024 Ehime Dietitian.